おはようございます。セア・トリハツです。日本選手権前夜に書いてます。
個人的な話ですが、初めてオートレースを観に行ったのは2023年浜松の日本選手権でした。
帰りのバスの車内でお爺ちゃんと喋ったの楽しかったです。浜松駅からは絶望的に遠かった。
この記事では、YouTubeに転がっていた大昔の日本選手権オートレースの映像を見た感想を書いていきます。
日本選手権はどんな大会?
日本選手権は、1965年から行われている最も歴史のある大会。オートレース日本一を決める一大イベントです。
最初の方は3月や2月にも行われていましたが、第12回大会(1980年10月)からは秋開催となっています。
現在では、全レースがオープンレースで行われています。シンプルに同条件でレースをして、最も強い選手を決める大会になっています。
現行ルールでは、優勝戦は5100m(500mを10周回)になっています。
第1回~第3回 ダート走路12車立て
第1回 1965年3月 川口
この頃のオートレースは現在とルールが違うようです。
- 1周がやたら長い。ストレート部分が結構な長さ
- スタートが手旗信号(大時計の故障時は今でも行われる)
- 12車立てでのレース(現行ではMAX8車立て)
- 走路がアスファルトではなくダート。砂の上を走っている
バイクでレースをしている、ということ以外はほぼ別物に見えます。
第2回 1965年11月 浜松
第2回の動画もありました。概要欄にはダート8250m(800m10周)と書いていました。
スタートラインからゴールラインが250mもあったみたいです。現在の2.5倍もありますね。
レース前に「最長ハンディは310m」って言ってたので、現代とはまるっきり別物のレースです。
レースの方は最軽ハンデの選手が逃げ切ってましたね。道中のデッドヒートみたいなものは全くなかったです。
第3回 1966年10月 飯塚
第3回は飯塚で開催。第2回はあまりにも離れすぎてレースにならなかったので、ハンデが見直されたようです。
概要欄には「ダート 600m(二級走路) 13周 7950m」と書いていました。当時の飯塚はスタートラインからゴールラインが150mあったようです。
砂の上を走っていて、13周あること以外は現代のそれに近いレースになっていました。
第4回以降 アスファルトの舗装路で8車立て
第4回 1968年3月 大井
第4回は大井オートレース場で開催。なお、この場は現存していません。
概要欄には「10周 舗装路 4800m」と書いていました。ついにアスファルトの走路になりました。
実況が「残り2周 1000m」とか「残り1周 500m」と言っていたので、1周500mのようです。
じゃあ1周目はハンデ位置によっては500m切っているのか…?
第5回 1970年3月 飯塚
飯塚では2回目の日本選手権。前回とは違いアスファルトの舗装路で8車立て。
概要欄には「5100m 10周回」と書いていたので、スタートラインからゴールラインが100mで1周500mという走路はこのころから変わっていないのかもしれません。
カメラが良くなって勝負服の色が見えるようになりました。
白、黒、赤、青は1人ずつですが、黄と緑が2人います。当時は競馬のように「枠」が採用されており、5枠と6枠が2人ずついました。
感想
大昔のオートレースを見た感想。
- ダートはコーナーでのせめぎあいが少なく退屈、あとコーナリングが滑ること滑ること。
- 第4回からアスファルトの走路になり、第5回にはほぼ現行ルールになっていた。
- ダートならできた12車立ては、アスファルトでやるとヤバそう。
1970年のレースが現代のレースと似たような感じになっているのは意外でした。
第6回以降もYouTubeに転がっていたので、また見てみようと思います。
それでは~。

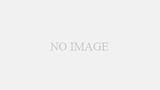
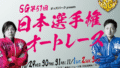
コメント